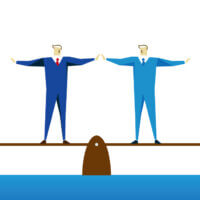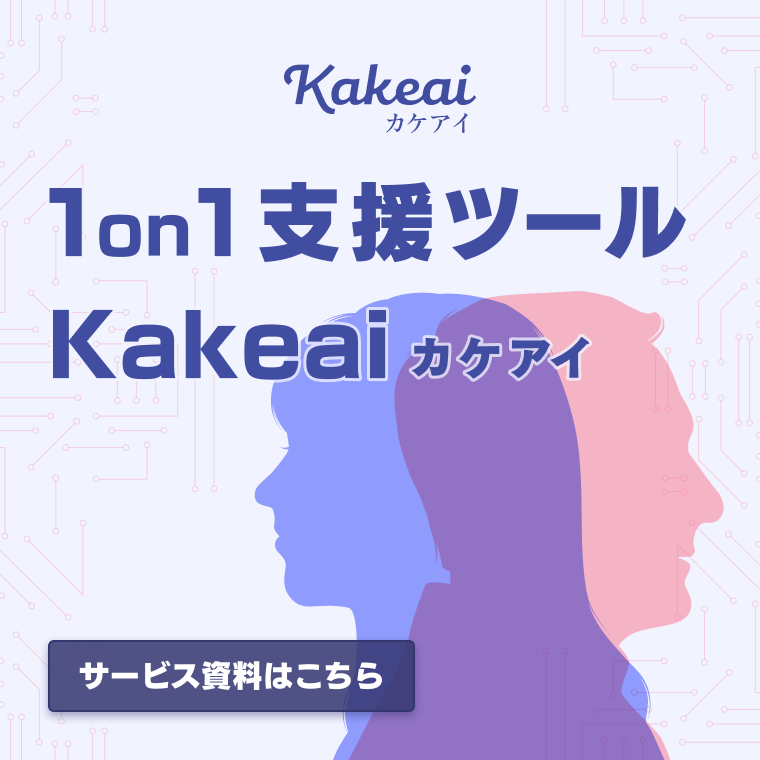スパン・オブ・コントロールをふまえたマネジメント
スパン・オブ・コントロールとは
管理職(上司)が直接連動して、管理できる人数を定義する考え方です。
もともとは軍の編成・組織構成において用いられていたものが、企業経営の世界にも適用されるようになりました。
組織設計においては、事業戦略の実行のために合理的かつ効率的であることと同時に、各組織内のマネジメントが適正に行うことができるような規模感を考慮する必要があります。
マイヤーとボーテでの研究(2000)では、スパン・オブ・コントロールが一定以上になると想定された成果が創出できないだけでなく、組織運営において悪影響が生じる可能性があることが指摘されています。
スパン・オブ・コントロールを適正に維持することで、組織的な成果の創出が可能になると言えます。
- スパン・オブ・コントロール(1人の管理職が直接管理できる人数)には上限がある
- スパン・オブ・コントロールの上限を超えると組織と個人の成果と成長に影響がある。
※スパン・オブ・コントロールは、管理スパンとも言います。
原則・管理職、部下の適正人数
一般的には5名~7名が望ましいと言われます。
つまり、1人の管理職に対して、5名~7名の部下であれば、管理職がそのマネジメントを適正かつ効果的に行うことができると考えられます。
1人の管理職が、所課の役割を遂行し目標やミッションを達成する活動を遂行するためのメンバーという観点だけでなく、部下の目標遂行状況を把握し評価をすることや、育成的な指導を行う上でも適正人数の限界があるとされています。
部下の人数制限は必要?
スパン・オブ・コントロールという言葉から管理職が部下に指示を出し、統制してコントロールするという意味にとり違えられていることもあります。
しかし、スパン・オブ・コントロールの考え方がさしているのは、あくまで「1人の管理職が適正に対応できる部下の人数です」。
また、組織のフラット化が進んでいる組織に属している人は、スパン・オブ・コントロールの考え方自体に違和感を抱くこともあるようです。
しかし、Google社ではProject Oxygen(プロジェクト・オキシジェン)の取組み・調査を通じて、マネージャー職は組織全体のパフォーマンスを高める上で、必要な存在だとし、組織にいるとパフォーマンスが高まる上司像を定義しています。
そこで掲げられていることは「ビジョンと戦略」「成果主義」「マイクロマネジメントをしない」などに加えて「専門知識と技術をもってアドバイスができるコーチであること」「部下のキャリア形成を支援すること」「部下の健康と成果を挙げることに関心を払うこと」「良き聞き手として、活発にコミュニケーションをとること」などが挙げられています。
Google社のProject Oxygenの示唆を踏まえても、組織の役割や部下の状況によってマネージャーが個々人とコミュニケーションをとるのは一定の組織の規模感の上限があると言えるでしょう。
実現できないケース
原則としてのスパン・オブ・コントロールの適正人数は参考値としながら、事業戦略を確実に実行していくための組織構造を考え、管理職とそこにどのような能力・志向の人材を配置すると実行力が高まるのかを考えながら組織を作っていくことが望ましいと言えます。
スパン・オブ・コントロールを超えやすい状況
- チーム内に複数カテゴリーの業務があり、メンバーがそれぞれ専門的な仕事をしている
- チーム内のメンバー間の連携が少なく、マネージャーとメンバーが1対1で対応することが多い
- マネージャー自身が、プレイヤーとしての業務に割く時間が多くならざるを得ない
組織設計上、ある機能を担う部署を複数おくことは業務遂行上非効率になることがあるため、特定の機能を一つの部署としてまとめようとする場合があります。
また、管理職へ昇進・昇格の運用上の問題や全社の人件費管理の関連からも簡単に管理職数を増やせないという状況がある場合は、理想的なスパン・オブ・コントロールが実現できないことも多々あります。
必ずしも正解はないものの、マネージャーが部下と対話をし、業務上必要な連携ができていない場合は、現実的な対応が必要になってくるでしょう。
部下の人数が限界を超えている場合
各所課の実態として管理職が、部下をマネジメントしきることが難しい状況の場合には、組織設計から見直しをする必要があります。
また、管理職が個人の業務を抱えていてマネジメント業務に時間を使うことができていない場合は、管理職の業務を見直すことも必要になってきます。
しかし、一般的には組織編成を見直すことは簡単ではありません。
そのような状況では、1つの所課の中でチーム制を導入するなど、業務と人材の管理がしやすい状況にすることが一つの対応策となります。
管理職の下に経験年数の長い従業員をリーダーとして任用する方法です。
1-3-9のチーム作り
1-3-9のチーム作りといわれるように、1人の管理職のもとに3名のリーダーの役割を設定し、そのリーダー1人1人が3名のメンバーをみるようにすると1人の管理職が12名のメンバーをみることができるようになります。
この場合は、リーダーにどこまで業務上の判断をしてもらうかなどの権限や考課を誰がどのように行うのかを予め明確にしておくとよいでしょう。
実際に仕事を進める中で「誰に何を聞いたら良いかが分からない」「管理職とリーダー職の意見が異なる」などの状況が起きるとメンバーは混乱しがちです。
管理職とリーダーが連携しながら動くことで、今の人員体制を前提としながらチームとしての動き方を加速していくことができます。
参考:Google’s Quest to Build a Better Boss
権限委譲(エンパワーメント)の進め方
エンパワーメント(Empowerment)とは、組織に所属する一人ひとりが、その組織の発展や変革のために力を発揮できる状態を指します。
権限委譲とも呼ばれ、上司の権限の一部を部下に渡して、部下の裁量で判断して仕事を進められるようにすることです。スパン・オブ・コントロールを超えたチームの場合も、チーム内をさらに小さなグループに分けて、そのグループごとにリーダーを配置する「チーム構成」を変更することと合わせて、そのリーダーに「権限や裁量」を与えて小グループが自律的に業務を進められるようにすることが必要です。
権限委譲を進める上で、まず重要なことは「責任の所在」を明確にすることです。
例えば、AマネージャーからBマネージャーに管掌範囲や権限を渡す場合には、同階層での権限の変更のために当然「責任」と「権限」がセットで変更になります。
しかし、AマネージャーからCリーダーに権限を委譲する場合には、最終責任はAマネージャーがとるもののその権限の一部をCリーダーに渡すことになります。
どの部分の権限をマネージャーがリーダーに渡すのか、その最終責任はAマネージャーがとることになるということを予め明確にしておくと、業務を進める中での混乱を最小化することができます。
また、権限の渡し方についても、リーダー層が自分で判断して進めて良い部分と、リーダーが自分で判断をする前に、マネージャーと認識のずれがないかを確認する必要があるケースを予め確認しておくと良いでしょう。
具体的には、業務の進め方や、他の部下の業務のクオリティの確認、チームの会議運営など実際の「業務」に関係する部分は権限委譲が進めやすいところです。
一方で、部下の評価・育成に関わる部分は、マネージャーが権限と責任をもって遂行する部分です。
とはいえ、部下の人数が多くすべての部下の業務遂行状況をマネージャーが把握しきれない場合には、リーダーと連携をしながら部下個々人の情報を収集し、リーダーに対応してほしいことを指示して他の部下に育成的な関り方をしてもらうことなどが望ましい関わり方といえます。
組織運用の変更事例
変更前の状況
- 1名のマネージャーに対して、30名以上のメンバーがいる状況で、経験のあるメンバーをリーダーという名称で役割をおいてはいたが、権限と責任はすべてマネージャーにある状況で、リーダーはメンバーが困った時の相談役という位置づけ。
- マネージャーが各メンバーに対して指示を出し、メンバーがマネージャーが承認・了承をして業務を進めるという流れであったため、現実的にマネージャーがすべての業務を見切れない。
課題認識
- 環境変化が激しい中で、マネージャーがすべてのメンバーの業務を把握して指示・判断をするのではなく、権限移譲を行い組織全体の対応力・対応スピードをあげていくこと。
- マネージャーが目の前の業務だけではなく、中期的な取り組みに着手するほか、メンバーに業務指示以上の育成的な関り方をすることで、メンバーの成長を促していくこと。
取り組み
- マネージャーはメンバーに対して、目標を明示してその達成と育成を支援しながら、部署の目標達成の最終責任をもつ役割とし、リーダーには実行プロセスの判断の権限をもちながら、メンバーの業務遂行を支援する役割として再定義。
- マネージャー1名に対して5名のリーダー、1名のリーダーに対して5~6名のメンバーとして部署内にチームを編成した。
- 目標管理や育成の責任はマネージャーにあるものの、日々の業務遂行状況や課題をマネージャーがリーダーから情報収集し、マネージャーとリーダーが連携して育成を進める。
取り組み上の留意点
- リーダーに対してマネージャーが業務上の判断やメンバーとの関わり方について育成的な指導をすることを含めて、権限移譲を進めること自体で一時的に業務負荷が高まるため、一律ではなくリーダーの状況に応じて権限移譲を進めた。
- チームの編成を見直しと同時に、チーム内の業務フローや会議体を見直し、業務効率を高められる点の洗い出しと効率化を行った。