
議論が進む!オンラインMTGの方法
テレワーク・リモートワークの中で、オンラインMTGがすっかり日常になりました。
ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなどのオンライン会議ツールの参加方法や画面の共有の仕方なども浸透し、会議の進行自体は問題ない。
そんな今だからこそ、「数年以上前から、オンラインで議論するのが当たり前」という方にオンラインMTGで意識していることを伺いました。
ファシリテーション「し過ぎない」
対面の場であれば「今、考えているんだな」「何か発言したい様子だな」ということを無意識でも把握できます。
しかし、オンラインでは圧倒的に参加者について得られる五感情報が少ないです。発言しようとしてタイミングが被ってしまうというということもよくあります。
だからこそ、「○○さん、どうですか?」と、みんなに発言をしてもらおうと順番に発言を促します。
しかし、あまり進行役がテキパキと進めてしまうと、参加者がそれぞれ発言するものの「みんなでの議論」になりにくくなってしまいます。
オンライン会議では、対面の会議よりもしっかりファシリテーションをした方が緊張感を作れますが、その上で「発言を待つ」間(ま)を恐れない進行が大事だと思います。(企画系・リーダー)
「同じ物」を見ながら一緒に考える
会議のアジェンダや関連資料を事前に共有して、会議のゴールを設定するといっても具体的な論点が分からないと議論が拡散しがちです。
そこで「何を決めればいいのか」だけではなく「今日の会議の論点は何なのか?」を「表」にしておくとメンバー全員が何について考えればいいのかズレなくなります。
例えば、いくつか選択肢がある中でどれが良いかを議論したい時には、その「選択肢の概要」と「特徴」の2行だけの「表」でも十分だと思います。
会議のオーナーが事前に準備をしておければ一番良いですが、オンライン会議で画面共有しながら会議の場で表をみんなで一緒に完成させるようなイメージで良いと思います。
オンライン会議の場合は、1つのゴールに向かって一緒に考えているという感覚を持ちにくいので、「みんなが同じものを見て一緒に考えやすい」ようにすると時間も効率よく使えます。
対面の場では「前向きに参加しているか」「共感しているか」「反対意見がありそうか」など、さほど意識しなくても参加者が議論の進度を把握できるシグナルがたくさんあります。
一方でオンライン会議の場合は、意識的にリアクションをしてもらわなければ、参加者全体がどう感じているかを把握するのは難しいものです。
とはいえ、オンライン会議は「場」の力を参加者が感じにくい環境だからこそ、雰囲気に流されないというメリットもあります。
事前のアジェンダの発信や資料の共有などの約束は共通認識にしつつ、チームにあったやり方を見つけていけると良いですね。


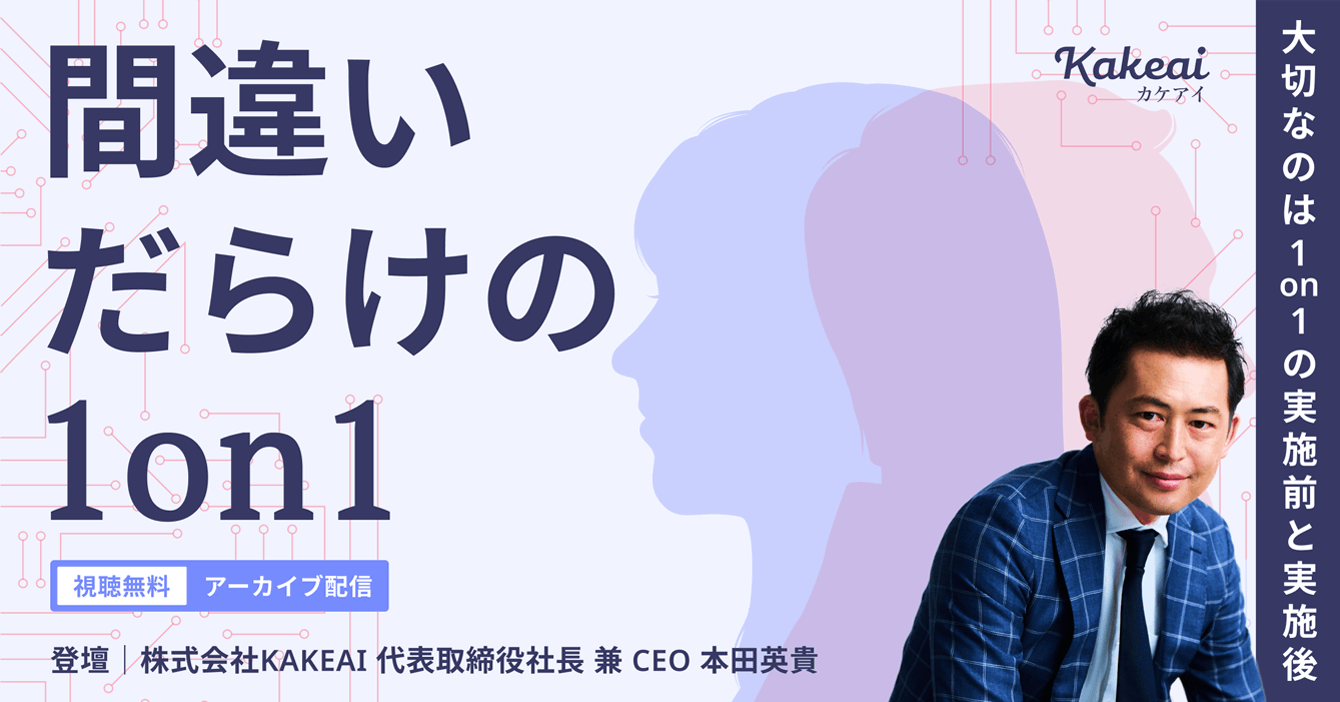


-17-3-200x200.jpg)











